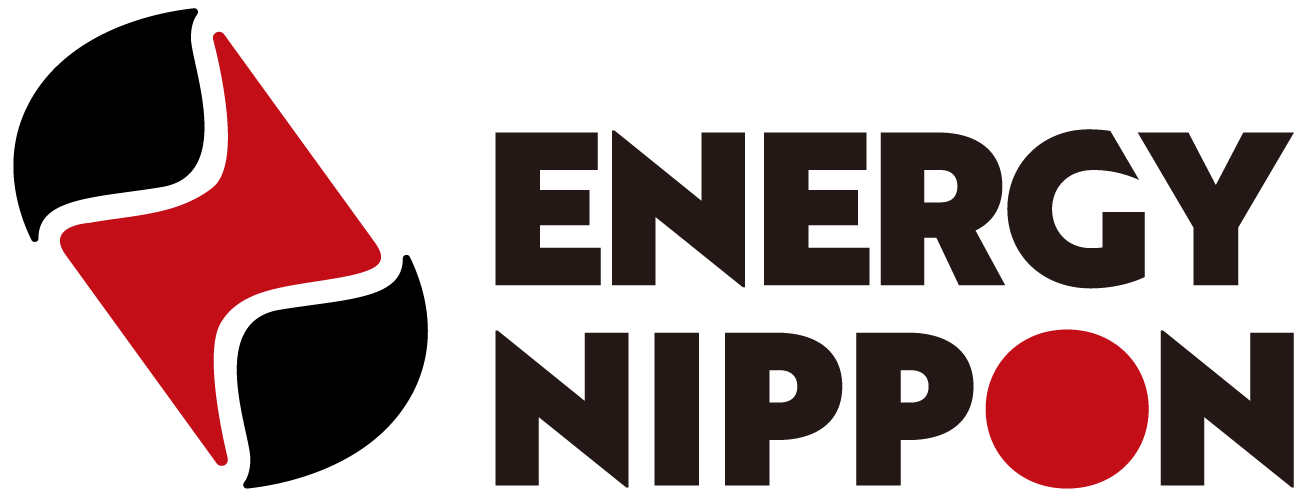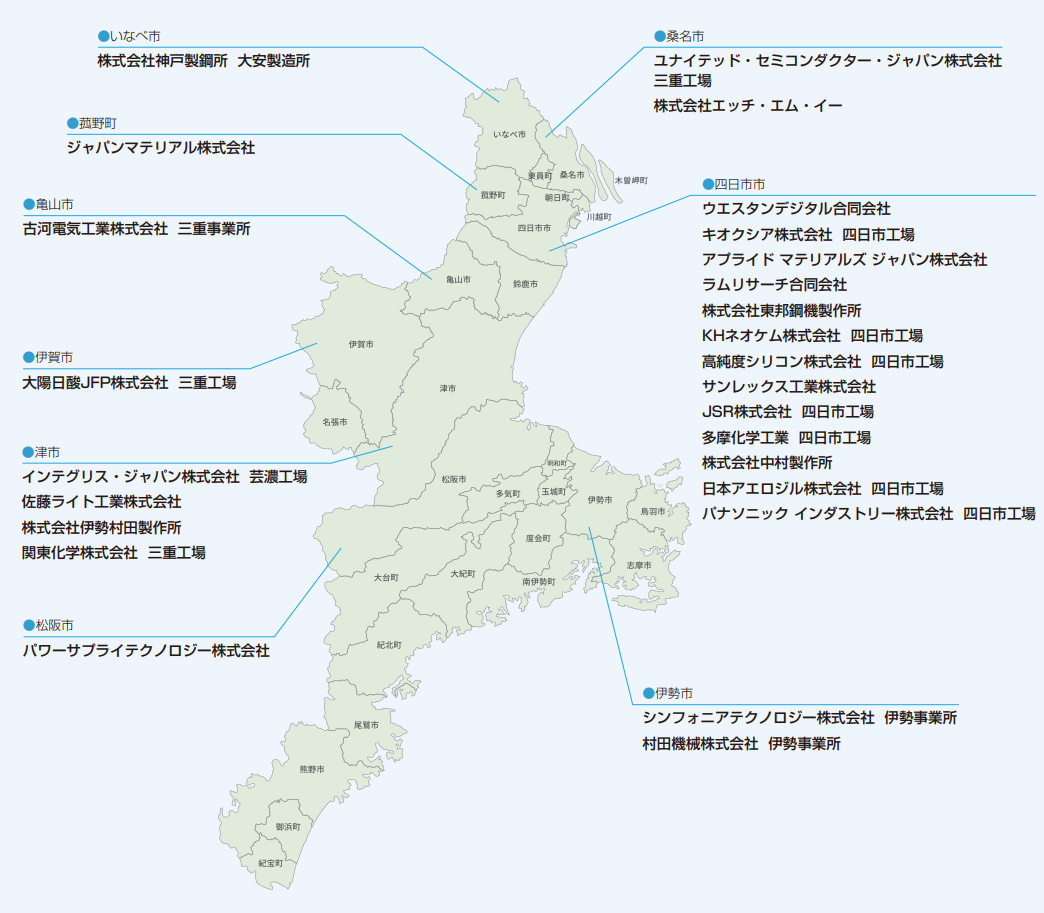日本における洋上風力の展望と課題を多角的に議論――WFOカンファレンス東京で開催
2025/07/09

2025年7月2日・3日、東京にて世界洋上風力フォーラム(WFO)主催の国際カンファレンスが開催された。国内外から官民のキープレイヤーが多数集結し、洋上風力――とりわけ浮体式洋上風力――の政策動向や事業化に向けた要件、財務・技術・安全といった多様な論点について、実務ベースでの活発な議論が展開された。
初日は、資源エネルギー庁の福岡功慶氏による基調講演を皮切りに、O&Mフェーズの財務パフォーマンスをテーマとしたパネルディスカッションが行われた。保険、金融、アナリティクスの各分野から専門家が登壇し、長期的な運用・保守段階における経済性の向上策について多角的な視点から意見が交わされた。
続くセッションでは、グローバルなサプライチェーンの需給動向や、発電所間における風干渉(ウェイク)の影響とその法的側面、さらに日本およびフランス・地中海地域での浮体式プロジェクトの紹介がなされ、洋上風力の技術的課題と国際的潮流を俯瞰する機会となった。加えて、日本航空による安全文化に関する講演と、HSE(健康・安全・環境)分野の専門家によるパネルでは、拡大する市場において人的安全をどのように担保していくかが議論された。
2日目は、浮体式洋上風力の商業化を軸にプログラムが構成され、国土交通省、金融機関、ディベロッパー、技術プロバイダーなど多様な立場から現実的な課題と今後の方向性が共有された。特に、オフテイク戦略(CPPA含む)や詳細なサイトデータの活用、プロジェクトリスクの適切な評価など、実務上直結するテーマが取り上げられた点は参加者にとって非常に実践的な内容となった。
午後のセッションでは、技術組合FLOWRAによる日本における技術開発の取り組み、カーボントラストの国際共同研究の進捗、さらにはポルトガルにおけるエネルギー政策と技術革新の事例紹介など、世界の先進事例を交えた議論が続いた。締めくくりとなったパネルディスカッションでは、ローカルコンテンツの確保や地域内連携の重要性が強調され、日本におけるサプライチェーンの強靭化に向けた方向性が探られた。
本フォーラムは、制度、技術、事業運営の垣根を越えた情報共有と連携強化の場として極めて有意義であり、日本の洋上風力市場の持続的成長に向けた大きな一歩となった。
このコンテンツはWindTAIWANにて公開されたものであり、
ENERGYNIPPONとのコラボレーションにより共有されています。