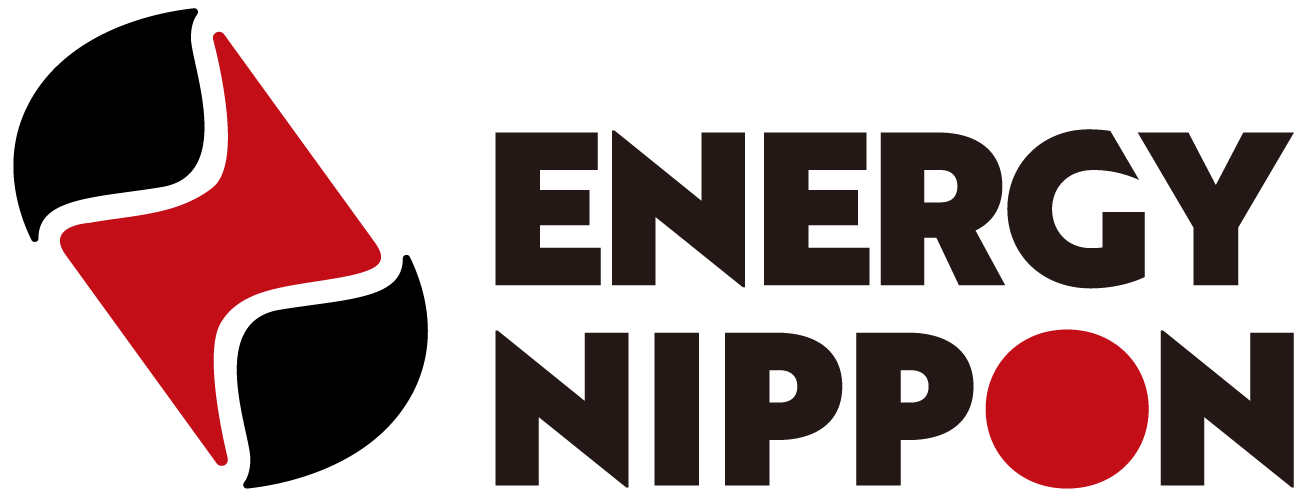捕らえるべきは風か、それとも機会か――日本の洋上風力が向かう先と、その教訓
2025/10/7
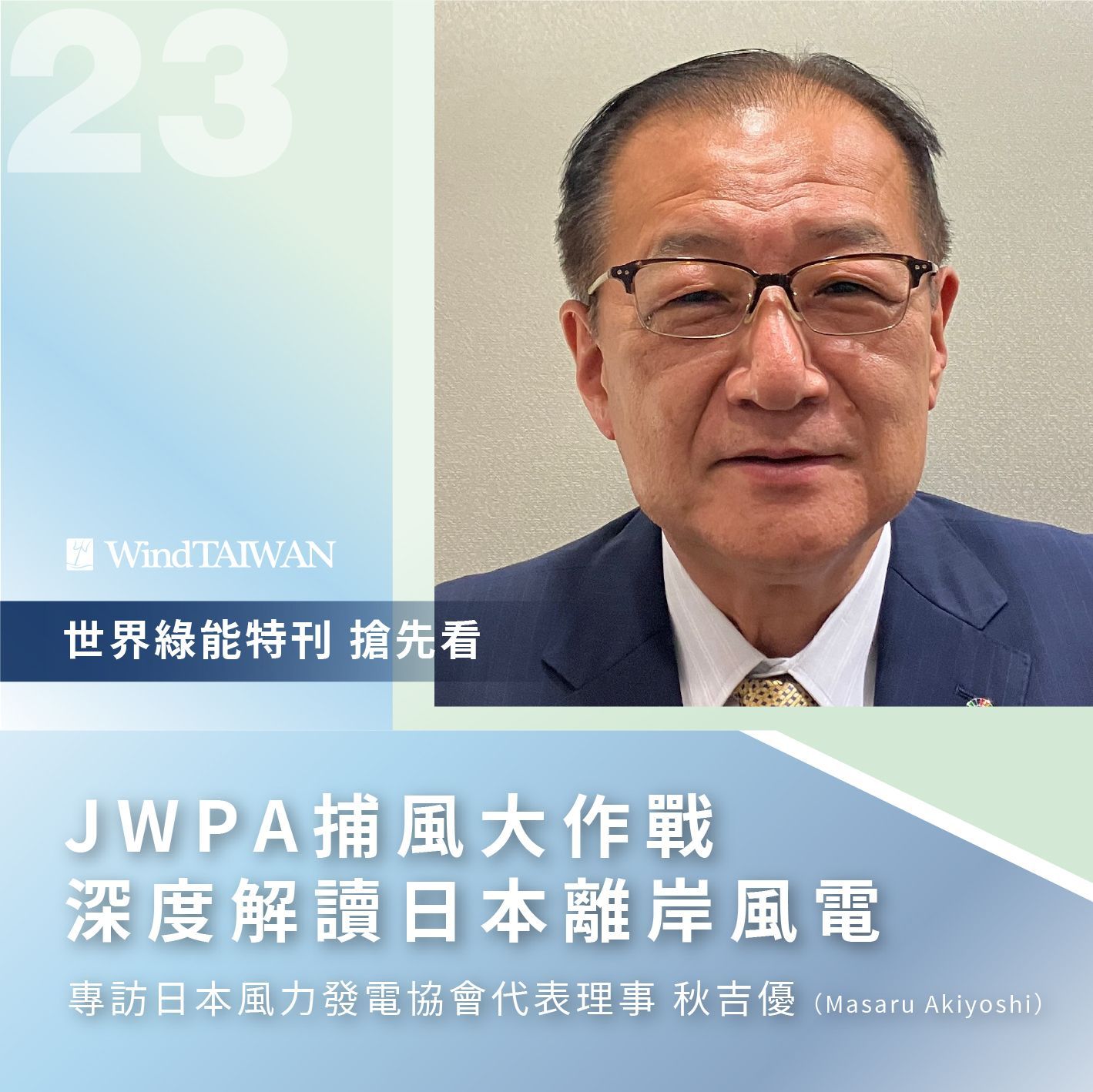
日本風力発電協会・秋吉優理事長インタビュー
2002年に制定された「エネルギー政策基本法」によって、日本のエネルギー戦略は「S+3E」──安全(Safety)、エネルギー安全保障(Energy Security)、経済性(Economic Efficiency)、環境(Environment)──という4本柱を軸に展開されてきた。以来、基本計画はほぼ3〜4年ごとに見直され、2025年2月には第7次エネルギー基本計画が公表されたばかりである。
中でも近年、政府が最重要課題として位置づけているのが「洋上風力発電」だ。2030年に装置容量5.7GW、事業形成ベースで10GW、2040年には30〜45GWという野心的な目標が掲げられている。
こうした動きを牽引する産業団体が、日本風力発電協会(JWPA)である。285の正会員と180の賛助会員、20の自治体会員を擁するこの団体は、風車メーカーから電力会社、建設業者、O&M企業、コンサルティングまで、風力発電の全バリューチェーンをカバーしている。
JWPAの秋吉優理事長によれば、2025年現在、日本で「成案化」された洋上風力プロジェクトは5.1GWに達しているが、そのうち実際に稼働しているのは0.3GWに過ぎず、残りはまだ着工に至っていない段階にある。実際、今まさに風車や主要部品の発注フェーズに入ったばかりの状況だという。
2021年に実施された初の洋上風力入札では、長崎県五島市、秋田県由利本荘市など4案件(計1.7GW)が落札された。だが、プロジェクトの実行段階でロシアによるウクライナ侵攻が勃発。資材価格の高騰や円安が直撃し、コストが急上昇。特に設備の多くが外貨建てで取引される日本にとって、この価格変動は致命的で、業者の経営を直撃している。
この危機に対し、日本政府は次回の第4次入札から「価格調整メカニズム」の導入を検討中だ。これは、契約時の物価と実際の発注時の物価の差を反映させ、電力価格を調整可能にするという仕組みだ。インフレに連動した柔軟な価格設定は、入札者にとって実質的な「命綱」となる可能性がある。
ただし、この制度はまだ検討段階にあり、正式な入札要項には盛り込まれていない。業界からは、過去の3件の既存契約にも同様の調整措置を適用すべきという声が上がっているが、どのタイミングで、どの範囲まで、どのような指標に基づいて適用するかといった具体的設計は、今後の政府と業界の協議に委ねられている。
目標と現実のギャップ、為替とインフレの波、グローバル供給網の再構築──。日本の洋上風力産業はいま、大きな試練の渦中にある。だが、その試練を乗り越える仕組みを構築できれば、台湾を含むアジアの他国にとっても大きな参考モデルとなるだろう。
このコンテンツはWindTAIWANにて公開されたものであり、
ENERGYNIPPONとのコラボレーションにより共有されています。